弔電とは?葬儀の観点からわかりやすく解説
葬儀で披露される「弔電(ちょうでん)」は、参列できない人が故人への哀悼を伝えるための正式な電報です。
しかし実際には、いつまでに送るのか、どんな文面にすべきか、受け取った側はどう対応するのかなど、迷いやすい点も多くあります。
この記事では、弔電の意味や成り立ち、送るときの基本マナー、受け取る側の対応までを整理して解説します。
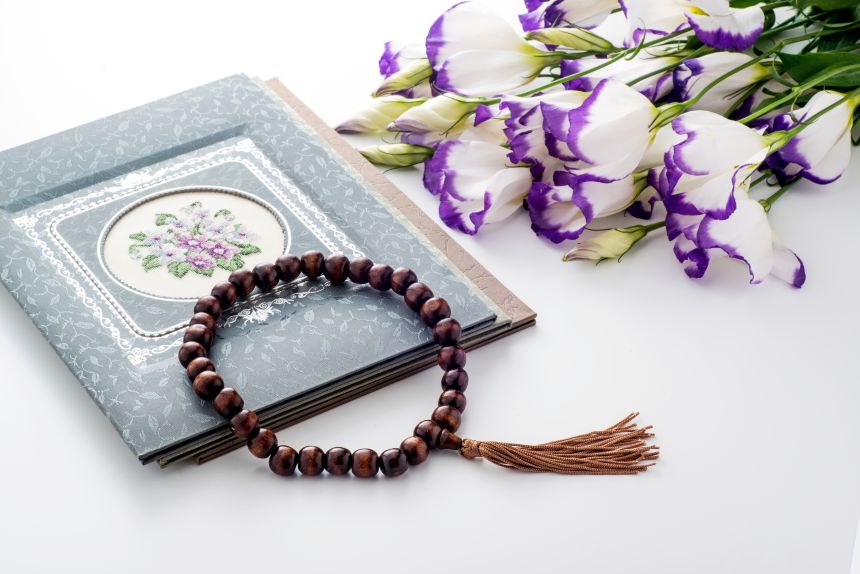
葬儀での弔電とは何か
弔電とは、葬儀に参列できない人が故人への哀悼と遺族へのお悔やみを正式な電報として伝えるための手段です。
もともとは遠方からでも気持ちを届けられる通信手段として使われ、現在では弔意を儀礼的かつ確実に届ける方法として広く利用されています。
葬儀全体の流れを理解しておくと、弔電の位置づけがより明確になります。詳しくは葬儀の流れ(はじめての方へ)をご覧ください。
弔電の読み方と表記
弔電(ちょうでん)は、「弔う」という字が示すように、故人をしのび悲しみを分かち合う意味を持ちます。
正式な葬儀文書や式次第では「お悔やみ電報」ではなく「弔電」と表記され、儀礼上の正式な言葉として定着しています。
会社や団体名義など、公的な立場で用いる場合には略語ではなく「弔電」という正式表記を使うのが望ましいとされています。
弔電の歴史と社会的背景
弔電は、明治期に電報制度が発達したことで葬儀文化に取り入れられた通信手段です。
当初は遠方の親族や知人が葬儀に間に合わない場合に弔意を伝えるために利用されました。
戦後には企業や団体間の弔意表明にも活用され、「時間に間に合う礼節の表現」として社会的に広く定着しました。
葬儀や通夜の違いについては、葬儀・通夜・告別式の違いも参考になります。
現代における弔電の位置づけ
現在の弔電は、個人・企業・団体を問わず、対外的に正式な弔意を伝える手段として機能しています。
特に次のような立場の人が送るケースが多く見られます。
- 会社・学校・自治体など、組織を代表して弔意を伝える場合
- 職場や地域の有志など、複数人の連名で代表者が送る場合
- 恩師・上司・師匠など、立場上直接参列できないが敬意を表す必要がある場合
弔電は、形式の整った言葉で哀悼を伝えることで、送り手と受け手の関係を公正に示す記録的な意味を持ちます。
形式が残るからこそ、相手の立場に敬意を払う手段として今も選ばれ続けています。
弔電を送るときの基本マナーと手配の流れ
弔電を送る際は、通夜までに届くよう早めに手配することが大切です。
宛名や文面、金額などにも一定の形式がありますが、基本の流れを理解しておけば難しくはありません。
ここでは、弔電を送るときに知っておきたい手順とマナーを整理します。
弔電の手配と宛先の基本
弔電は、通夜の開式前に届くよう手配し、葬儀式場の喪主宛に送るのが基本です。
通夜に間に合わない場合は、告別式の開始前に届くように手配すれば問題ありません。
弔電が通夜までに届くことで、遺族が内容を確認し、どの弔電を告別式で披露するかを選ぶ時間を確保できます。
式場や喪主の情報は、訃報連絡や葬儀案内で確認するのが確実です。
案内が届いていない場合は、葬儀を担当している葬儀社に問い合わせても差し支えありません。
葬儀の全体像を把握しておくと、弔電を送るタイミングの判断がしやすくなります。詳しくは葬儀・通夜・告別式の違いも参考になります。
宛先の基本:
- 宛名は「喪主 ○○様」または「○○家ご遺族様」とする
- 送付先は「葬儀会場」または「斎場」の住所宛
- 喪主名が不明な場合は「○○家様」でも問題なし
手配方法と文面作成のポイント
弔電は、NTTや郵便局などの公式サイトを利用すれば、インターネット上で文面入力から配達指定まで一度に手配できます。
オンラインの申込みでは定型文が用意されているため、初めてでも安心です。
文面は「故人への哀悼」と「遺族への労り」を中心に、簡潔で丁寧な言葉を選ぶことが基本です。
宗派や地域によって言葉の違いがあるため、特定の宗教表現や忌み言葉(重ね言葉、直接的な表現など)は避けましょう。
| 避けたい言葉の例 | 理由 | 代替表現 |
|---|---|---|
| 重ね重ね・ますます・再び | 不幸が重なることを連想させる | 心より・深く・謹んで |
| 死亡・急死など直接的な表現 | 遺族への配慮に欠ける印象になる | ご逝去・ご永眠 |
葬儀中に多くの人が耳にする内容であるため、中立的で形式を整えた文体が求められます。
到着の確実性を最優先にし、文面は定型文をもとに短く整えると失敗がありません。
葬儀での言葉遣いに不安がある場合は、葬儀の挨拶(例文)も参考になります。
金額の目安と複数人で送る場合
弔電の料金は、個人では1,500〜3,000円、会社や団体では3,000〜5,000円程度が目安です。
台紙や文字数によって価格が変わるため、見栄えよりも確実に届くことを優先するのが良いでしょう。
弔電の目安料金(参考)
| 送る立場 | 料金の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 個人 | 1,500〜3,000円 | 一般的な台紙を使用 |
| 会社・団体 | 3,000〜5,000円 | 上質台紙や代表名義で送る場合 |
複数人で送る場合は代表者を立て、「〇〇株式会社一同」や「〇〇同窓会」など連名形式で明記します。
形式よりも「誰からの弔意か」が伝わることを意識し、全体の負担が偏らないように調整することが大切です。
金額の相場感については、葬儀費用の平均相場を参照しておくと全体の見通しが立てやすくなります。
弔電を受け取ったときの対応とマナー
弔電は、通夜から告別式にかけて遺族が整理し、葬儀社と相談しながら扱いを決めます。
通夜までに届くのが理想ですが、告別式の開式前に到着するケースも珍しくありません。
届いた弔電はすべて確認したうえで、告別式で披露する数通を選定します。
ここでは、弔電の披露・保管・お礼の流れを順を追って説明します。
葬儀での披露(読み上げ)の基本
弔電は、告別式で代表的な数通を司会者が読み上げるのが一般的です。
読み上げ件数は3〜5通程度で、全てを披露する必要はありません。
披露する弔電は通夜後に遺族と葬儀社が確認し、故人との関係や公的立場などを踏まえて決めます。
披露対象を選ぶ際の主な基準:
- 故人や喪主と関係が深い個人・団体からの弔電
- 勤務先・学校・地域団体など公的性格のあるもの
- 式全体の時間配分や重複を考慮して選定
読み上げの順番は、団体→個人の順など関係性に配慮して決められます。
披露の流れをより具体的に知りたい場合は、告別式とは?の記事も参考になります。
披露しなかった弔電の扱い
披露されなかった弔電も、すべて遺族の手元に渡り、正式な弔意として受け止められます。
葬儀後にあらためて確認し、送り主への感謝を心に留めて整理します。
どの弔電も、遺族にとっては故人を悼む思いの記録として大切なものです。
通夜から告別式までの進行を把握しておくと、弔電の整理や選定の判断がしやすくなります。
流れを確認したい場合は、葬儀の流れ・所要時間の記事が参考になります。
弔電へのお礼・お返し
弔電のみの場合は、基本的に個別のお返しは不要です。
香典や供花を伴う場合にのみ、返礼品やお礼状を検討します。
弔電は「気持ちを伝える儀礼」であり、返礼を前提とするものではありません。
会社や団体から届いた弔電には、代表者宛に簡潔なお礼を伝えると丁寧です。
その他の弔電は、忌明けの挨拶状などで一括して感謝を伝えるのが一般的です。
お礼文の書き方に迷う場合は、葬儀の挨拶(例文)が参考になります。
弔電を正しく理解し、状況に応じた形で弔意を伝える
弔電は、時間や距離の制約がある中でも、相手に誠意を伝えられる確かな手段です。
参列が難しい場合でも、通夜や告別式に合わせて手配すれば、正式な形で弔意を届けることができます。
遺族にとっても、弔電は多くの人が故人を思い、心を寄せてくれた証として後に残る大切なものです。
訃報を受けたら、まず葬儀式場や喪主の情報を確認し、できるだけ早く弔電を手配しましょう。
時間に余裕があれば、文面や台紙を丁寧に選び、香典や供花とのバランスも考慮します。
一方で受け取る側は、届いた弔電を一つひとつ丁寧に扱い、披露・保管・お礼の流れを落ち着いて整理することが大切です。
弔電は形式的なものに見えますが、時代が変わっても相手への敬意と誠意を形に残す手段としての価値を持ち続けています。
状況に合わせて無理のない範囲で活用し、故人と遺族への思いを丁寧に届ける姿勢を大切にしましょう。
よくある質問
- 弔電はいつまでに送ればいいですか?
-
通夜までに届くのが理想ですが、告別式の開式前に届けば問題ありません。
通夜後の夜間に申し込んでも、翌朝に式場へ届くサービスもあります。
訃報を受けたら、できるだけ早めに手配するのが安心です。 - 弔電はどこに、誰宛に送ればいいですか?
-
送付先は葬儀式場宛、宛名は喪主名が基本です。
喪主が不明な場合は「〇〇家ご遺族様」としても差し支えありません。
訃報連絡や葬儀案内で式場名と喪主名を確認してから申し込むと確実です。 - 弔電の文面はどのように書けばよいですか?
-
文面は「故人への哀悼」と「遺族への労り」を中心にまとめます。
忌み言葉や宗教に偏った表現を避け、短く誠実な言葉でまとめましょう。
弔電サービスに用意されている定型文を利用すれば、形式に沿った文面が整います。 - 弔電の費用はどのくらいが目安ですか?
-
個人では1,500〜3,000円、会社や団体では3,000〜5,000円程度が一般的です。
金額は台紙の種類や文字数によって変わりますが、見栄えよりも到着の確実性を優先します。 - 弔電を受け取った場合、お礼は必要ですか?
-
弔電のみであれば個別のお返しは不要です。
香典や供花が伴う場合のみ、返礼品やお礼状を検討します。
一般的には、忌明けの挨拶状で一括して感謝を伝える形が丁寧です。

この記事の監修者
むすびす株式会社 代表取締役社長兼CEO 中川 貴之
大学卒業後、株式会社テイクアンドギヴ・ニーズの立ち上げに参画。2002年10月葬儀業界へ転進を図り、株式会社アーバンフューネスコーポレーション(現むすびす株式会社)を設立、代表取締役社長に就任。明海大学非常勤講師。講演・メディア出演多数。書籍出版

















