葬儀と通夜と告別式の違いは何?それぞれの言葉の意味を解説
「葬儀」「通夜」「告別式」という言葉は、日常的に耳にするものの、その違いを正しく理解している人は多くありません。
案内状を受け取ったときに「どちらに参列すべきか」「香典はいつ渡すのか」と迷うことも少なくないでしょう。
実際、現代の葬送習慣では地域や慣習によって形式が異なるため、あいまいなままでは対応に戸惑う原因となります。
この記事では、まず「葬儀・通夜・告別式」の意味を整理し、全体の流れの中での位置づけを解説します。
さらに、目的や参列者、香典の扱いの違いを比較し、自分がどちらに参列すべきかを判断するための基準を提示します。
基礎知識と参列マナーをあわせて理解することで、葬儀に臨む際の不安を解消し、故人や遺族に対して失礼のない対応ができるようになります。
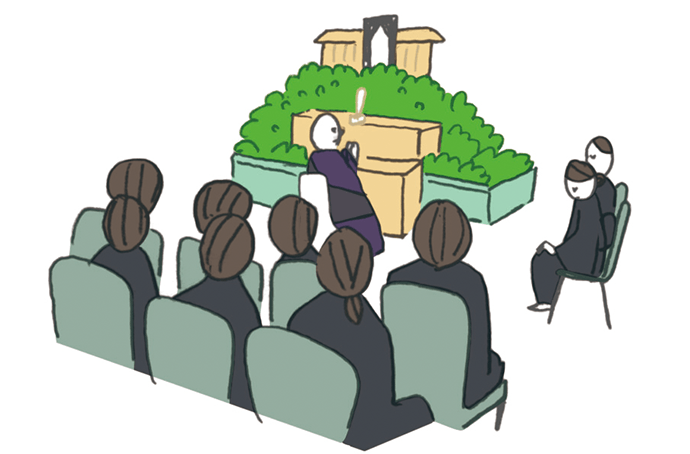
葬儀・通夜・告別式はそれぞれ意味が異なり、混同しやすい言葉を正しく整理できます
葬儀・通夜・告別式は同じ場面で使われがちですが、本来はそれぞれ異なる意味を持ちます。
葬儀は僧侶の読経など宗教的な儀式、通夜は故人と最後の夜を過ごす場、告別式は最終の別れを行う場です。
現代では通夜と葬儀・告別式を含めて「葬儀」と呼ぶ使われ方も一般的です。
この違いをあらかじめ整理しておくと、案内状や会話で混乱せず、参列や準備の判断がしやすくなります。
葬儀は宗教的な儀式を指し、現代では通夜と告別式を含む全体を示す言葉としても使われます
葬儀は本来、僧侶の読経や法要を通じて故人の冥福を祈る宗教的な儀式を指します。
一般的にはこの葬儀に続いて告別式が行われ、遺族や親族を中心に最終の別れを告げます。
一方で日常会話では、通夜と葬儀・告別式をまとめて「葬儀」と呼ぶ広義の用法も定着しています。
通夜は、遺族や親しい人が故人と最後の夜を過ごす儀式です
通夜は、遺族や親しい人々が集まり、故人と一夜を共にして冥福を祈る儀式です。
本来は夜通し灯明や線香を絶やさず過ごしましたが、現代では読経と焼香を中心に短時間で営まれる形が一般的です。
開始は18〜19時ごろ、読経・焼香で約1時間、通夜振る舞いを含めて全体で2時間程度が目安です。
告別式は、故人との最終のお別れを行う儀式であり、親族を中心に営まれます
告別式は葬儀に続いて営まれ、故人との最終の別れを行う儀式です。
現代では平日日中に行われることが多く、参列者は親族や特に近しい人が中心となる傾向があります。
通夜が「弔問の場」であるのに対し、告別式は「葬送の本儀」としての意味を持ちます。
葬儀全体の流れを把握すると、通夜と告別式がどの場面に位置づけられるかが分かります
一般的な流れは、臨終から搬送・安置・納棺を経て通夜を営み、翌日に葬儀・告別式と火葬を行います。
1948年施行の法令により死後24時間以内の火葬はできないため、臨終の当日から翌日にかけての即時進行は原則ありません。
実務上の打ち合わせや火葬場の予約調整も加わり、通夜は臨終から2〜3日後、その翌日に告別式・火葬という進行が主流です。
通夜は葬儀の前夜に営まれ、夕方から夜にかけて行われます
通夜は前日に営まれ、開始は18〜19時ごろが一般的です。
読経・焼香で約1時間、通夜振る舞いを含めて全体で2時間程度を見込みます。
仕事や学校のあとに参列しやすい時間帯であるため、幅広い人が弔問に訪れます。
告別式は翌日の午前に営まれ、火葬まで半日を要します
告別式は10〜11時ごろ開始が多く、儀式は1.5〜2時間ほどです。
その後に火葬場へ移動し、火葬・収骨に1.5〜2時間程度を要するため、全体で半日ほどの所要になります。
都市部では火葬場の混雑により日程が延びることがあります
都心部では火葬場の予約が混み合い、臨終から葬儀まで7日前後、場合によっては10日程度待つこともあります。
一方、地方では2〜3日以内に通夜・葬儀が営まれることが一般的です。
日程の延伸は地域事情によるもので、失礼にはあたりません。
通夜と告別式の違いを比較すると、目的・参列者・香典の扱いの差が明確になります
通夜は幅広い関係者が参列しやすい弔問の場、告別式は親族や近しい人が中心の最終のお別れの儀式です。
両者の違いを整理しておくと、参列判断や香典の準備がしやすくなります。
目的の違いを理解すると役割が整理できます
通夜は弔意を示し、死を受け止めるための儀式です。
告別式は葬送の本儀として営まれ、故人を送り出す最終の儀式にあたります。
参列者の範囲は、通夜の方が幅広く、告別式はより親族中心です
通夜は夕方〜夜に行われるため会社関係や友人なども参列しやすく、広い範囲の弔問が集まる傾向があります。
告別式は平日日中に営まれることが多く、親族や特に近しい人が中心となります。
香典の扱い方にも地域差があるため確認が必要です
香典は通夜か告別式のどちらか一度で構いません。
都市部では通夜で渡すのが一般的ですが、地方では告別式で渡す地域もあります。
| 項目 | 通夜 | 告別式 |
|---|---|---|
| 目的 | 弔問の場として死を受け止める | 葬送の本儀として最終のお別れを行う |
| 参列者 | 会社関係・友人・近隣など幅広い | 遺族・親族・特に親しい人が中心 |
| 時間帯・所要 | 夕方〜夜/約2時間 | 午前開始/儀式1.5〜2時間+火葬1.5〜2時間 |
| 香典 | 都市部は通夜で渡すのが一般的 | 地方は告別式で渡す地域もあり |
参列するなら通夜か告別式か、関係性に応じた判断基準を得られます
参列は故人との関係性で判断します。
親族や特に親しい友人は通夜と告別式の両方、仕事関係や知人は通夜のみでも十分に弔意を示せます。
両方に出られなくても、一方の参列で失礼にはなりません。
- 遺族・親族・親友など近しい関係 → 通夜と告別式の両方
- 勤務先・取引先・知人など広い関係 → 通夜のみでも可
- 遠方や都合で難しい → どちらか一方で十分
参列できない場合は香典や弔電で弔意を示せます
参列が難しい場合は、香典を現金書留で送る、弔電を葬儀会場や遺族宅に手配するなどの方法があります。
形式よりも気持ちが伝わることが大切で、誠意のこもった対応を選べば失礼にはなりません。
通夜と告別式における香典マナーを理解すると、失礼のない対応ができます
香典は通夜か告別式のいずれかで一度渡せば十分です。
地域差はあるものの、本質は「供養の気持ち」を形にすることにあります。
香典を渡すタイミングと基本マナーを押さえておきましょう
香典は通夜か告別式のどちらか一度で渡します。
受付で袱紗から取り出し、一礼して両手で差し出すのが基本です。
都市部は通夜、地域によっては告別式で渡す慣習があります。
香典の金額や作法を理解すると安心です
金額の目安は、親族で3〜10万円、友人・知人や仕事関係で5千円〜1万円が一般的です。
不祝儀袋を用い、宗派に応じて「御霊前」「御仏前」などと表書きをします。
詳細は 香典マナーの解説 を参照してください。
違いと流れを理解すれば、葬儀にどう向き合うか迷わなくなります
用語の違いと全体の流れを把握しておけば、参列や香典の準備に迷わず臨めます。
地域差や慣習の違いはありますが、基本を理解していれば大きな失礼にはつながりません。
大切なのは形式を完璧に守ることではなく、故人と遺族に敬意をもって対応することです。
基礎を押さえ、自分の立場に応じて適切な行動を選べるようにしておきましょう。
よくある質問
- 葬儀と告別式は同じ意味ですか?
- 葬儀は本来、僧侶の読経や法要を中心とした宗教的儀式を指し、告別式はその後に営まれる最終のお別れの儀式です。現代では両者をまとめて「葬儀」と呼ぶことも多いため、使い分けに注意が必要です。
- 通夜と告別式、どちらに参列するべきですか?
- 親族や親しい友人は両方に参列するのが一般的ですが、知人や仕事関係の方は通夜のみでも十分に弔意を示せます。両方に出られなくても、一方への参列で失礼にはなりません。
- 通夜や告別式に参列できない場合はどうすればよいですか?
- 参列できない場合は、香典を現金書留で送る、または弔電を葬儀場や遺族宅に手配する方法があります。参列そのものよりも、弔意が誠実に伝わることが大切です。
- 香典は通夜と告別式の両方で渡す必要がありますか?
- 香典は通夜か告別式のどちらか一度で十分です。都市部では通夜で、地方では告別式で渡す習慣が多くみられます。複数回参列しても繰り返し渡す必要はありません。
- 葬儀の日程はどのくらいかかりますか?
- 一般的には臨終から2〜3日後に通夜、その翌日に葬儀・告別式と火葬を行います。ただし都市部では火葬場が混み合うため、7〜10日程度待つこともあります。

この記事の監修者
むすびす株式会社 代表取締役社長兼CEO 中川 貴之
大学卒業後、株式会社テイクアンドギヴ・ニーズの立ち上げに参画。2002年10月葬儀業界へ転進を図り、株式会社アーバンフューネスコーポレーション(現むすびす株式会社)を設立、代表取締役社長に就任。明海大学非常勤講師。講演・メディア出演多数。書籍出版

















