自宅葬における流れを解説
自宅葬は、葬儀会館を使わず自宅で故人を見送る葬儀の形式です。
家族の思いに寄り添い、落ち着いた環境で最期の時間を過ごせる点から、近年あらためて関心が高まっています。
しかし、自宅での葬儀には斎場での葬儀とは異なる準備や段取りが求められるため、喪主となる方にとっては進め方に不安を感じやすいのも事実です。
特に「通夜はどう進めるのか」「火葬の流れは通常と違うのか」といった実務的な流れが見えないままでは、冷静な判断が難しくなります。
この記事では、自宅葬における一連の流れを時系列に沿って整理しながら、喪主の立場で知っておきたいポイントを解説します。
初めて葬儀を取り仕切る方でも、全体像を把握しやすいよう各工程ごとに段取りと注意点をまとめています。
ご家族の意向に沿った、自宅での落ち着いた見送りを実現するための判断材料として、ぜひご活用ください。

自宅葬では、一般的な家族葬と同様の流れを自宅で行うことになる
自宅葬は、自宅を式場として使用する点を除けば、通夜・葬儀・告別式・火葬といった基本的な流れは、斎場や葬儀式場で行う葬儀とほとんど変わりません。場所が異なるだけで、儀式の進行順や必要な対応は基本的に同様です。
喪主としては、自宅という慣れた環境で進められる安心感がある一方で、式場としてのスペース確保や参列者への対応、設備面の準備、近隣への配慮など、特有の対応が求められます。これらは事前の段取り次第で大きく左右されるため、早い段階で葬儀社と具体的な流れを共有しておくことが不可欠です。
実際の自宅葬では、まず故人の安置を行ったあと、通夜、葬儀・告別式、火葬という順序で進みます。これらの工程は、斎場や式場を使う葬儀と大きな違いはなく、宗教儀礼の形や式次第も基本的には変わりません。ただし、自宅という場所に応じて、人数調整や時間配分の工夫が必要になることもあります。
自宅葬は、形式に縛られず家族の想いを反映しやすい一方で、準備や運営の負担が喪主側にかかりやすい傾向があります。滞りのない進行のためには、経験のある葬儀社と連携しながら、現実的なスケジュールと動線をあらかじめ整えておくことが重要です。
事前準備では、会場の確保と葬儀社との打ち合わせが重要
自宅葬を行うには、まず自宅を葬儀の場として使用できるかどうかを早い段階で確認し、それを踏まえて葬儀社と具体的な打ち合わせを進めることが求められます。こうした初期対応が、その後の準備と当日の進行を円滑にする前提となります。
喪主はまず葬儀社に連絡を入れ、自宅での実施が可能かを相談します。建物の構造や立地、近隣の環境などによっては、棺の搬入が難しいケースや、式を行うスペースが十分に確保できない場合もあるため、現地確認を行ったうえで判断することが大切です。
実施が可能と判断された場合は、葬儀の流れに沿って必要な準備を並行して進めていきます。たとえば、以下のような項目が代表的な準備内容となります。
- 葬儀社への連絡・相談
- 自宅の使用可否や安置スペースの確認
- 導師(僧侶)や火葬場の手配
- 必要備品や式中の動線の調整
- 近隣住民への配慮・あいさつ
とくに駐車スペースの確保や、参列者の出入りによる騒音などは、近隣トラブルの要因となりやすいため、事前の声かけや説明を欠かさないことが重要です。
こうした準備を滞りなく進めるためには、経験のある葬儀社と早めに連携し、進行の全体像を把握したうえで段取りを固めていくことが有効です。限られた時間の中でも、要点を押さえた計画によって喪主の心理的・実務的な負担を大きく軽減できます。
通夜〜火葬まで、基本的には家族葬と同じ順序で進行する
自宅葬においても、通夜から火葬までの一連の流れは、家族葬や一般葬と同じく決まった順序で進行します。喪主は自宅という場の特徴を踏まえつつ、標準的な葬儀の流れを基準に段取りを整えることが基本となります。
具体的には、故人を自宅に安置した後、通夜、葬儀・告別式、火葬、収骨という一連の工程を順に実施します。儀式の構成やタイミングそのものは変わらず、宗教形式がある場合はそのしきたりに従って進める点も同様です。違いがあるとすれば、各工程を行う空間が専門式場ではなく、自宅という点にあります。
自宅を使用することで、式の時間配分や演出にある程度の柔軟性が生まれます。たとえば、弔問者の来訪時間をある程度調整したり、告別式の式次第を簡略化するなど、状況に応じた調整が可能になります。ただしその反面、運営や進行に対する責任の一部が喪主側に委ねられるため、葬儀社との綿密な調整が不可欠です。
あくまで基本の流れを守ることで、参列者や宗教者の混乱を防ぎ、落ち着いた葬儀を実現することができます。自由度と確実性のバランスをとることが、自宅葬を成功させるための鍵となります。
通夜では、弔問客への対応と式の進行に喪主が目を配る
自宅葬における通夜では、弔問に訪れた人々が故人と静かに向き合える時間を整えることが重要です。喪主は儀式の進行を滞りなく進めるとともに、弔問客に対する最低限の礼節を保つよう心がける必要があります。
通夜は本来、遺族や親しい関係者が故人と最後の夜を過ごす場であるとともに、弔問客が故人に別れを告げるための時間でもあります。そのため、自宅という私的な空間で行う際には、儀式の格式を保ちつつも、参列者が落ち着いて故人を偲べる雰囲気を整えることが求められます。
喪主の具体的な役割としては、僧侶や葬儀社との式次第の確認、焼香や読経の進行に合わせた案内、挨拶の準備などが挙げられます。また、弔問客の到着・退出時の対応や通夜後の振る舞いの有無についても、事前に決めておく必要があります。自宅で行う場合、参列者の動線や靴の脱ぎ履き、トイレの使用といった細部への配慮も大切です。
形式的な流れを守りつつも、空間としての限界や個別の事情に応じた柔軟な対応が必要になるのが、自宅葬の通夜の特徴です。葬儀社と連携しながら事前に進行を確認し、喪主としての負担を軽減しつつ、参列者にとっても過ごしやすい場を整えていくことが大切です。
通夜前に、僧侶や葬儀社と式次第を確認する
通夜の進行を滞りなく行うためには、事前に僧侶や葬儀社と式の流れを細かく確認しておくことが不可欠です。特に自宅という限られた空間では、動線や時間配分に無理がないように調整することが求められます。
僧侶の到着時間や読経の開始時刻、焼香の順番と回数、弔問客の規模など、通夜当日の具体的な要素は事前にすり合わせておく必要があります。また、自宅のスペースに応じて僧侶の位置や焼香台の設置場所を決め、弔問者の導線も想定しておくと、当日の混乱を防ぐことができます。
特に自宅葬では、一般の式場と異なり係員の人数が限られることが多く、喪主や遺族が一部の進行補助を担う場面も出てきます。そのため、当日使う仏具や供花の配置、読経に要する時間、通夜後の流れ(通夜振る舞いの有無など)も含めて事前に確認しておくことが重要です。
全体の流れを把握しておくことで、喪主が場当たり的な判断に追われることを避けられます。葬儀社に確認すべき内容をリスト化し、式の前に共有しておくと、精神的な負担も軽減されます。
通夜中は、喪主としての挨拶や会葬者対応が求められる
通夜の時間中、喪主は儀式の進行を見守りつつ、参列者への丁寧な対応と、適切な場面での挨拶を行う役割を担います。儀式を無事に終えるためには、所作や立ち位置だけでなく、全体の雰囲気にも気を配る必要があります。
基本的な流れとしては、僧侶による読経が始まり、弔問客が順に焼香を行い、最後に喪主が挨拶を行うという順序が一般的です。喪主の挨拶は、参列者への感謝を述べるとともに、故人の人柄や生前の関係に触れることで式全体を締めくくる役割があります。
また、自宅葬の場合は、参列者の導線や焼香の順序に迷いが出やすいため、葬儀社の補助を受けながらスムーズに案内できるよう事前の確認が不可欠です。とくに人数が多い場合やスペースが限られている場合には、焼香台の配置や移動ルートをあらかじめ調整しておくと安心です。
通夜後に通夜振る舞い(軽食など)を行うかどうかも、あらかじめ方針を決めておき、参列者に失礼がないよう配慮することが望まれます。形式にとらわれず、家庭の事情に応じた対応で問題はありませんが、事前に決めておくことで当日の対応が落ち着いて行えます。
葬儀・告別式は、故人を正式に見送る重要な儀式となる
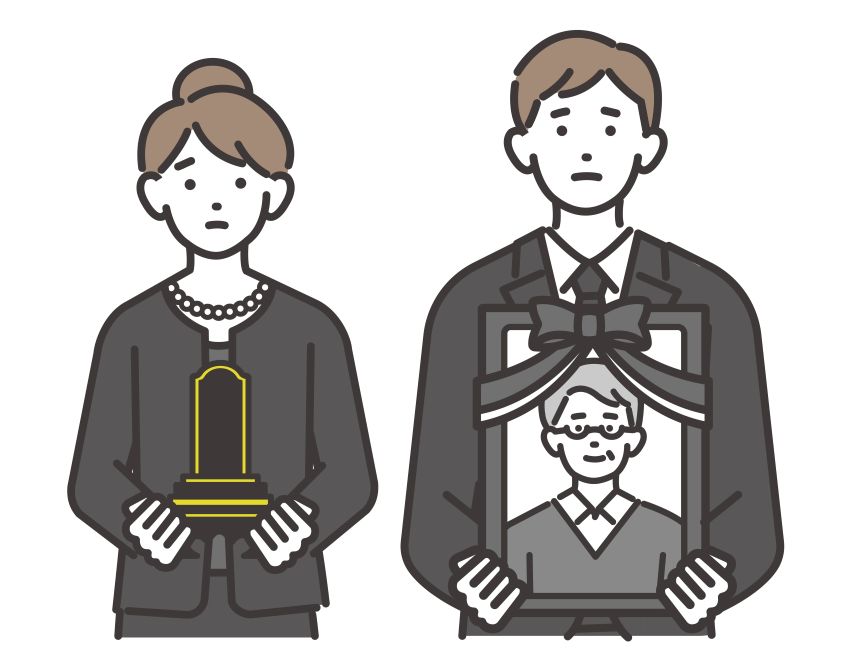
葬儀・告別式は、通夜に続く本儀式として、故人との最期の別れを公に執り行う場です。喪主は遺族を代表して式を整え、参列者に感謝の意を示す役割を果たします。自宅で行う場合でも、その意義や儀式の流れは変わらず、一定の厳粛さを保つことが大切です。
一般的には、僧侶による読経や焼香、弔辞、喪主挨拶、閉式の辞といった流れで進みます。自宅葬の場合は式場と異なり空間に限りがあるため、参列者の配置や動線、仏具の置き方など、細かな調整が必要になります。また、葬儀と告別式を同時に行う「一日葬」に近い形式をとることも多く、時間の管理も重要なポイントです。
喪主にとって特に求められるのは、式全体を通しての統率力と心配りです。葬儀社や僧侶と事前に流れを確認し、供花や弔電の整理、焼香の案内、挨拶の段取りなどを滞りなく準備しておくことで、式を通して遺族や参列者が落ち着いて故人を偲べる環境が整います。
自宅という私的空間で式を行うことで、形式にとらわれない演出や進行も可能となりますが、儀式としての基本的な流れを保つことで、参列者にとっても違和感のない見送りが実現します。柔軟性と礼節の両立を意識した準備が、納得感のある葬儀につながります。
式前には供花・弔電・参列者対応の確認が必要
葬儀・告別式を円滑に進行させるには、開始前の段階で供花や弔電、席次などの配置や段取りを整理しておくことが重要です。細かな準備を事前に整えておくことで、式中の対応に余裕が生まれ、喪主の負担軽減にもつながります。
たとえば供花は、贈り主の名前が並ぶため、その並び順や配置の仕方に配慮が求められます。弔電についても、全文を読み上げるか一部のみ紹介するかをあらかじめ決めておき、順番や読み手を明確にしておくことで進行が滞りません。
また、参列者の席順や焼香の順番なども、式直前に決めておくことで、現場での混乱を避けることができます。とくに自宅葬では会場スペースに限りがあるため、供花や弔電の設置場所も工夫し、動線や視認性に配慮したレイアウトが求められます。
これらの準備は喪主が単独で判断するのではなく、葬儀社と相談しながら確認していくことで、見落としを防ぎつつ確実性を高められます。確認リストをもとに、式直前の打ち合わせで最終確認を行っておくと、当日の進行がスムーズになります。
とくに確認しておくべき主な項目は以下の通りです。
- 供花の配置や並び順
- 弔電の読み上げ順と差出人名の確認
- 席順(席次)の最終調整
- 受付や焼香の動線の整理
式中は、喪主の挨拶・焼香・閉式が進行の要となる
葬儀・告別式の進行では、僧侶による読経から始まり、弔辞・焼香、喪主挨拶、閉式といった一連の流れが式の中心を成します。喪主はそれぞれの場面を円滑につなぐ役割を担い、参列者にとって落ち着いて故人と向き合える空間を整えることが求められます。
読経の時間は宗派や僧侶によって異なりますが、一般的には20〜30分程度が目安です。その後に行われる焼香では、参列者が順に故人へ哀悼の意を示します。焼香の誘導やタイミングは葬儀社の補助を受けつつ、喪主が全体の流れを把握しておくことが大切です。
弔辞が予定されている場合は、誰が話すか、どのタイミングで読み上げるかをあらかじめ調整しておきます。そして式の終盤には、喪主が代表して参列者への感謝と、故人との別れに対する想いを簡潔に伝える挨拶を行います。閉式の案内も喪主の一声によって締めくくられることが多いため、言葉の内容や順番を事前に準備しておくと安心です。
式全体が滞りなく進行することで、参列者は精神的に落ち着いた状態で故人を見送ることができます。喪主の所作や挨拶は、式の印象に大きく影響を与える場面でもあるため、形式にとらわれすぎず、故人や家族らしさを踏まえた自然な進行を意識するとよいでしょう。
火葬では、同行・収骨を経て式全体が完結する
火葬は葬儀の最終工程にあたり、喪主は火葬場への同行と、収骨における中心的な役割を担います。自宅葬の場合は、火葬場への搬送手順や出棺時間に特有の調整が必要となるため、通常の式場葬とは異なる点を把握しておくことが大切です。
火葬当日は、葬儀・告別式が終わり次第、自宅から霊柩車で火葬場へ向かう流れとなります。斎場や会館を使用する場合は火葬場と提携していることも多くスケジュールが整いやすいのに対し、自宅葬では火葬場との移動距離や混雑状況によって出棺時間を柔軟に調整する必要があります。特に、地域によっては火葬場の予約時間が限られており、午前中しか火葬を受け付けないといったケースもあります。
出棺のタイミングは、読経の終了時間や弔問者の人数、自宅から火葬場までの移動所要時間などを踏まえて設定する必要があります。また、自宅の周囲で霊柩車の駐車や出棺に制約がある場合もあるため、事前に確認しておくことが重要です。喪主は、葬儀社や火葬場職員の指示を受けながら、参列者への案内や収骨時の流れを把握しておくと安心です。
火葬と収骨を経て、葬儀全体が一区切りとなります。心身の疲労が出やすい時間帯でもあるため、無理のないスケジュールで動くことが大切です。自宅葬においては、移動の段取りを含めた事前の調整が円滑な運営を左右するため、火葬場の事情や地域の慣習に応じて、早めに確認・手配しておくことをおすすめします。
火葬場では、所要時間や控室での過ごし方を知っておく
火葬には1〜2時間を要し、その間は控室で休憩して待つことになります。待機時間の過ごし方は火葬場によって異なり、施設によっては精進落としの食事をとることができる場合もあります。一方で、飲食が制限されている火葬場では、軽食やお茶程度にとどめる対応が一般的です。
精進落としは、本来は火葬後に僧侶や親族を招いて行う感謝の食事ですが、現代では火葬中に簡略化して行われるケースも少なくありません。施設や喪家の方針に応じて、実施の有無や内容を事前に決めておくことが重要です。
遺族同士で静かに語らう時間にもなるため、控室の環境や案内方法も含めて、葬儀社と相談しながら準備を進めると安心です。
収骨後は、葬儀社の案内に従って帰宅・片付けを進める
火葬・収骨を終えたあとは、自宅に戻り、返礼品の整理や近隣へのお礼、室内の整備など、喪主として進めるべき後処理を整えていくことになります。香典返しや挨拶まわりなどは、必ずしも当日中に行う必要はなく、後日対応でも問題ありません。
なお、自宅葬で使用した祭壇や仏具、椅子などの備品は、多くの場合、葬儀社が設営から撤収まで一括して対応します。撤収作業は式終了後すぐに行われるケースが一般的ですが、立ち合いが必要な場合もあるため、事前に時間帯や段取りを確認しておくと安心です。
また、近隣住民へのお礼も重要な対応事項です。通夜や出棺による車の出入り、参列者の往来など、何らかの形で近隣に影響が及んでいる可能性があるため、簡単な手土産を添えて一言お詫びと感謝を伝えることで、丁寧な印象を残すことができます。地域によってはこのようなあいさつが慣例となっている場合もあります。
葬儀後の実務は想像以上に多く、喪主がすべてを単独で対応するのは負担が大きくなりがちです。家族や親族と役割を分担し、必要に応じて葬儀社にも継続的に相談しながら、無理のない形で進めていくことが望まれます。
自宅葬を円滑に進めるには、事前準備と周囲への配慮が不可欠
自宅葬を円滑に進めるためには、早い段階での段取り確認と、環境整備・近隣への配慮などを含めた総合的な準備が不可欠です。喪主の負担を軽減しながら、葬儀全体をスムーズに進行させるには、事前の調整と関係者との連携が重要になります。
自宅葬は斎場や式場を使用しないため、時間や内容の自由度が高く、家族の意向を反映しやすい反面、準備・進行・対応の多くを遺族側が担うことになります。たとえば、式を行う部屋の片付けや動線確保、参列者の受け入れスペースの調整、さらには騒音や出入りに関する近隣への配慮など、会場葬では生じにくい課題が多く含まれます。
これらの実務負担をひとつずつ整理するためには、葬儀社との打ち合わせを早めに行い、式の流れ・必要な物品・地域の火葬場事情などをすり合わせておくことが大切です。特に自宅の構造や立地によっては、棺の搬入経路や駐車スペースの確保など、事前確認が不可欠な要素もあります。
自宅葬を選ぶ背景には、家族で静かに見送りたいという思いや、形式に縛られない送り方への希望があります。その意義を大切にしながらも、円滑に執り行うためには、家族・葬儀社・地域との調和を意識した準備が欠かせません。無理のない運営体制を整えることが、喪主としての冷静な判断と行動を支える基盤となります。
自宅で行うことで生じる制約と工夫点を把握する
自宅葬には、スペースの制限や生活環境の調整、近隣への配慮といった特有の制約がありますが、これらは事前の確認と外部支援の活用によって十分に対応することが可能です。制約の存在を前提にした準備が、実行時の混乱を防ぐ鍵となります。
代表的な課題としては、部屋の広さや導線の確保、駐車スペースの有無、近隣住民への影響(車の出入りや焼香時の混雑)、衛生管理などが挙げられます。例えば、集合住宅や間口の狭い一戸建てでは棺の搬入に制限がある場合もあり、事前に搬送経路を確認する必要があります。また、焼香や読経の際に出る音や香りが、近隣に影響を及ぼす可能性がある点にも注意が必要です。
こうした制約に対しては、葬儀社が提供するレンタル設備(式用の椅子・祭壇・テントなど)や補助スタッフの手配を活用することで、現実的な解決が可能です。また、空間が限られている場合には、通夜と葬儀を少人数制で実施したり、オンライン配信などを検討する事例もあります。衛生面については、ドライアイスや冷却装置による安置管理が標準的に行われています。
自宅での制約は避けがたい一方、工夫次第で式の質を損なうことなく柔軟に運営することができます。問題点を可視化したうえで対応策を講じる姿勢が、喪主の精神的な余裕にもつながります。葬儀社との相談を通じて、環境に応じた最適な形式を選択していくことが重要です。
自宅葬ならではの主な制約と、それに対する主な対応策は以下のとおりです。
| 課題 | 対応策 |
|---|---|
| スペースが限られている | 少人数での実施、テントや椅子のレンタル |
| 騒音や出入りによる近隣への影響 | 事前のあいさつ、式時間の調整 |
| 搬入経路が狭い・複雑 | 葬儀社による事前確認と代替案の提案 |
| 衛生面の不安(夏季など) | ドライアイスや安置用冷却装置の使用 |
信頼できる葬儀社との連携が、自宅葬成功の要となる
自宅葬を円滑に進めるには、葬儀の流れや準備項目を把握するだけでなく、それらを確実に実行できる体制を整えることが欠かせません。そのためには、経験と実績のある葬儀社と密に連携し、段取りや当日の運営における不安を解消しておくことが重要です。
自宅葬では、会場手配や進行スタッフの常駐がない分、葬儀社の支援が大きな比重を占めます。安置の設備や搬送経路の確認、式場としてのレイアウト提案、近隣への配慮事項など、細部にわたる判断を喪主が単独で行うのは困難です。そうした場面で、現場経験が豊富な葬儀社の提案力と実務力は、極めて大きな支えになります。
また、自宅葬に対応する葬儀社は限られる場合があるため、依頼先を決める際は、複数の葬儀社を比較し、自宅葬に関する実績や対応可能な設備・スタッフ体制などを確認することが効果的です。事前相談を通じて、費用や段取りを可視化しておくことで、当日の判断がより的確になります。
形式や流れに自由度のある自宅葬だからこそ、計画の曖昧さが混乱の原因になりかねません。信頼できる葬儀社との連携は、準備の精度と当日の安定運営に直結します。喪主自身がすべてを背負い込まず、適切な支援を得ながら進めていく姿勢が、自宅葬を円滑に成功させるための大きな要素です。
よくある質問
- 自宅葬では、式の時間帯を自由に決められますか?
- 基本的には可能ですが、僧侶や火葬場の都合、参列者の来訪時間を考慮する必要があります。とくに火葬場は地域によって受付時間が限られており、午前中の出棺が求められるケースもあります。自由度がある一方で、全体の流れに支障が出ないよう事前の調整が重要です。
- 棺を自宅に運び込めるかどうかは、どのように判断しますか?
- 住宅の構造や搬入口の幅、階段・エレベーターの有無などにより判断されます。葬儀社が事前に自宅を下見して可否を確認してくれるのが一般的です。搬入が難しい場合は、安置場所や式の実施方法を変更する提案を受けることもあります。
- 自宅葬では、どの程度まで会葬者を招いてよいのでしょうか?
- 明確な制限はありませんが、自宅のスペースや動線、安全面を考慮すると、一般的には10〜30名程度までの少人数で実施されることが多いです。参列者が多い場合は、通夜と告別式で時間帯を分けて案内するなど、調整する方法もあります。
- 近隣住民へのあいさつはどこまで必要ですか?
-
必須ではありませんが、出入りが多くなる通夜・出棺の前後には、騒音や車両の出入りで影響を与える可能性があります。そのため、近隣住民に簡単なあいさつや一言断りを入れておくと、トラブル回避につながります。地域によっては習慣化されているケースもあるため、葬儀社に相談すると安心です。
配慮すべき主なポイントは以下のとおりです。
- 騒音や車の出入りが予想される前日〜当日のあいさつ
- 簡単な説明書きやお知らせ文の配布
- 必要に応じて菓子折りを添える(地域性による)
- 式後の簡単な御礼の言葉や報告も効果的
- 精進落としは必ず行う必要がありますか?
- 精進落としは形式的に必須ではなく、家族の方針や体力的な負担に応じて省略することも可能です。火葬中に軽食として行う場合や、収骨後に自宅で簡単に済ませるケースもあります。無理のない範囲で、感謝の気持ちを伝えられる形式を選ぶのがよいでしょう。

この記事の監修者
むすびす株式会社 代表取締役社長兼CEO 中川 貴之
大学卒業後、株式会社テイクアンドギヴ・ニーズの立ち上げに参画。2002年10月葬儀業界へ転進を図り、株式会社アーバンフューネスコーポレーション(現むすびす株式会社)を設立、代表取締役社長に就任。明海大学非常勤講師。講演・メディア出演多数。書籍出版

















