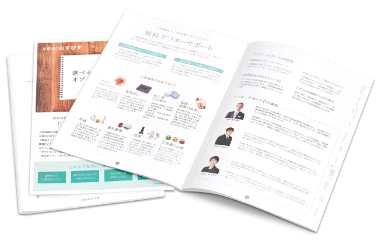ご葬儀のスタイルについて
よくあるご質問
- 骨葬とは、どのようなお葬式ですか?
- 故人様の火葬を終えられた後に、ご遺骨となった故人様とお別れすることを骨葬と言います。 一般的なご葬儀の流れは、お通夜、葬儀・告別式、火葬という順で進行します。骨葬を選ばれるのは、お通夜、葬儀・告別式、火葬までをお身内だけで行われ、日を改めて故人様とご縁のあった方々をお招きし、お別れの時間を過ごしたいとお考えのご家族様です。 骨葬は本葬やお別れ会とも言われ、これまでは著名人や企業の役員など、多くのご参列者様が見込まれる場合や、故郷にある菩提寺で改めてご葬儀を行う場合に選ばれていました。 最近では、お身内だけでご葬儀を行い、最後のお別れの時間をゆっくり過ごしたいというご家族様にも選ばれています。 なお、一部の地域では、お通夜の後に火葬を行い、葬儀・告別式を迎える骨葬を行うことが一般的なところもあります。
- 無宗教のお葬式で、お経を上げてもらうことはできますか?
- 可能です。無宗教葬とは、形式のない自由なかたちのお葬式ですから、お式でお寺様のお経が終わった後に、献花で故人様を偲んだり、故人様がお好きだった音楽を流すことができます。 ただし、菩提寺様とのお付き合いがあるご家族様は、菩提寺様に無宗教葬の形式で、お経だけあげてもらえるのかどうか、ご相談されたほうがいいでしょう。 お式中だけでなく、お式を終えられた後の火葬中もお経をあげてもらうことはできます。お時間は5分から10分と限られた時間の中でのお経となります。
- 社葬の対象になるのは、どんな人ですか?
- 会社に多大な貢献をした方です。会社によって考え方はそれぞれですが、一般的には社長や会長、役員までが対象となります。また、業務中に殉職された方も、対象となる場合があります。社葬を行うかどうかは、役員会で決められます。
- 社葬とお別れ会の違いは何ですか?
- 一般的に、社葬は読経や焼香などの宗教儀礼を重視して、葬儀会場で行われるお別れです。 お別れ会は、献花や音楽で送る、宗教色のないお別れです。ホテルやレストラン、本社ビルや店舗など様々な場所で行われます。お別れ会は偲ぶ会と呼ばれることもあります。
- 一般葬のメリットは何ですか?
- 一般葬には、家族葬にはない3つのメリットがあります。 ご葬儀後の弔問対応の負担を抑えることができます。 一般葬は、ご家族様やご親族以外にも、故人様と生前にご縁のあった多くの方と、1度にお見送りができるご葬儀です。家族葬のように参列できなかった方が個別にご自宅へ弔問に訪れ、その都度対応するといった負担を抑えられます。 故人様とご縁のあった方々の想いに応えることができます。 多くの皆様に、故人様へのお気持ちを伝えたり、お顔を見ることができる、最期の機会を用意できます。特にご縁の深かった方にとって、お世話になったお礼や感謝の想いを伝えることができる、大切な場となります。 参列者から伺う思い出を通じて故人様を偲ぶことができます。 故人様とご縁があった多くの方が参列されるので、たくさんの思い出を伺うことができます。時には、ご家族様もご存じない、故人様の思いがけない、新たな一面を知ることもあります。
- 一般葬と家族葬の違いを教えて下さい。
- ご葬儀にお呼びする方の範囲が違います。家族葬は、ご家族様やご親族など故人様と身近な方々だけでお別れするご葬儀です。 一般葬は、故人様と生前にご縁のあったご友人や、お仕事関係、ご趣味のサークル、ご近所の方など、一般の方を幅広くお呼びするお葬式です。そのため、一般葬は家族葬に比べて参列者の人数が多くなる傾向にあります。 また、一般葬にはご家族様にとって面識がない方が参列される場合があります。そうした方々へ故人様に代わって参列された感謝をお伝えするために、一般葬は家族葬よりも、しきたりやおもてなしが重視されます。
- 火葬式でも、お経をお願いすることはできますか?
- お通夜や告別式を行わず、火葬炉の前で故人様とお別れいただく火葬式でも、ご僧侶にお経を上げていただくことはできます。火葬炉での読経の時間は約10分です。 ただし、菩提寺とのお付き合いのあるご家族様は、まずは菩提寺にご相談ください。菩提寺によっては、お通夜や告別式といった宗教儀礼を行わない火葬式という送り方をお認めではない方もいらっしゃるからです。菩提寺のご了承がないまま火葬式を行った場合、納骨を断られることもありえますので、必ずご相談ください。 菩提寺とのお付き合いのないご家族様には、宗派に合わせて読経していただけるご僧侶をご紹介いたします。
- 家族葬に呼ぶかどうか迷った人は、呼んだほうがいいですか?
- 故人様だったら最期に会いたいと思われるか、お考えいただいた上で、決められたほうがよろしいでしょう。 お呼びしなかった方から後日、「どうして葬式に呼んでくれなかったのか」と言われるのではないかとご心配の方には、ご家族様のお考えや、お呼びするかどうか迷われている方とのご関係を伺った上で、アドバイスいたします。
- 家族葬には、家族や親戚以外の人を呼んでもいいのですか?
- 家族葬には、お呼びする方の範囲に決まりはないので、問題ありません。家族葬とは、故人様と親しく、故人様と最後にお別れしていただきたいという方をお呼びするご葬儀のかたちだからです。私たちがお手伝いする家族葬には、近しいご友人も参列されます。
- 1日葬なのに、葬儀会場の使用料が2日分かかるのはなぜですか?
- ご葬儀は1日だけですが、準備にもう1日必要なため、葬儀会場の使用料が2日分かかります。 告別式は午前に行われるので、式の前日に祭壇などの設営をしなければ、開式に間に合わないからです。 葬儀会場によっては、1日分の使用料に設定されているところもあります。
- 家族葬でも受付を頼んだほうがいいですか?
- 参列する方が、喪主様のご兄弟やお子様などご家族様だけであれば、受付を頼むことはありません。 ご親族や近しいご友人も参列し、香典を受け取ったり、返礼品を渡すのであれば、受付を頼んだほうがいいでしょう。 受付には、ご家族様の中でも、故人様の血縁ではないご長男の配偶者の方などをお選びください。血縁の方を選ばないのは、すぐにお焼香の順番が回ってきたり、参列者への対応で、受け取った香典の管理まで気が回らないことがあるからです。
- 家族葬に呼ばない親族には、どんな対応が必要ですか?
- 訃報の案内で、「故人や家族の意志により、家族だけで葬儀を行う」ことを伝え、ご親族の会葬辞退をお知らせしましょう。訃報と併せて、電話でも家族葬を行うお話しをすることで、より丁寧に、誤解なく会葬辞退を伝えることができます。
- 参列者が家族や親族だけなので、会葬返礼品は必要ありませんか?
- 喪主様のご兄弟やお子様など、ご家族様だけが参列する場合は、会葬返礼品を用意しないことがあります。 喪主様の奥様のご両親やご兄弟、従兄弟様など、ご親族も参列する場合は、用意したほうがよろしいでしょう。 会葬返礼品は、お通夜や告別式に参列する方へ、故人様に代わって感謝の気持ちを込めてお渡しするお品です。渡さなかった会葬返礼品は返品もできるので、用意しても無駄になることはありません。
- 親族への案内で注意することはありますか?
- 家族葬をごく近しいご親族だけで行った場合、お呼びしなかったご親族とのお付き合いに響くことがあることです。お呼びしなかったご親族から、後になって「どうして呼んでくれなかったのか」と連絡があることもございます。お呼びしないことで、今後のお付き合いに響くようなご親族がいらっしゃらないか、ご確認いただいたほうがよろしいでしょう。
- 1日葬とはどんなお葬式ですか?
- お通夜は行わず、告別式の1日だけでお別れいただくお葬式です。従来のお通夜・告別式2日間のお葬式に比べて、高齢の方でもお疲れを感じられることがなく、ご会葬される皆様のご都合も合わせやすいお別れです。ご葬儀の費用を抑えられることも特徴のひとつです。
- 無宗教葬はどのような流れで進行するのでしょうか?
- 無宗教葬に決まった流れはありません。お経やお焼香といった宗教の儀礼がないからです。献花やお柩を囲んでのお食事など、ご家族様がご希望される内容を伺いながら、一緒に進行をお考えいたします。
- 火葬式と直葬は違うのですか?
- どちらも同じ、お通夜や告別式を行わず、火葬だけで見送るご葬儀のかたちです。
- 火葬式での食事はどうするのですか?
- 火葬式はお通夜・告別式がないので、お通夜後に召し上がっていただくお清めはご用意いたしません。火葬中での精進落としをご希望のご家族には、火葬場の控え室にお食事をご用意いたします。
- お別れ会を行う場合の服装は、どうご案内すればいいのでしょうか?
- お別れ会の内容や場所によって異なります。企業や団体など、組織が主体となってホテルなどで行われる際は、喪服が相応しいでしょう。一方、ご家族様やご友人など、身近な方々がレストランなどで行われる際は、平服でも構いません。 平服の場合、男性は明るすぎないお色のスーツとネクタイ、女性も派手ではないスーツやワンピースをお召しの方が多く見られます。 服装に迷われた場合は、お別れ会の経験豊富なスタッフがお別れ会の内容を伺った上で、アドバイスいたします。いつでもご相談ください。
- お別れ会とは何ですか?
- 一般的にお別れ会は、ご親族や近しいご友人だけでご葬儀や火葬を行われた数日後に、故人様と生前に親交のあった知人や会社関係の方々に、お別れをしていただくセレモニーです。 「偲ぶ会」や「送る会」とも呼ばれ、有名人や著名人だけでなく、一般の方々にとっても身近となったお別れ会は、ご会葬者の人数が数名様から数百名様までの規模で、幅広く行われています。 宗教や形式にとらわれないお別れの場なので、ご僧侶による読経もご焼香もない、音楽や映像、照明などを取り入れた、自由なお別れのかたちもお選びいただけます。火葬後に行われる場合は、故人様のお体のままではお運びできないホテルやレストラン、ホールといった施設もご利用いただけます。 どのようなお別れ会にするのか、具体的なイメージを描くことが難しいとお考えの方には、経験が豊富なエンディングプランナーがこれまでの事例をご紹介し、ご家族様のご希望を伺いながら、進行から演出までプランニングいたします。
- 大手企業でなくても、社葬を執り行うものですか?
- 私たちが社葬をお手伝いした企業様は、大手ばかりではありません。 社葬とは、企業の発展に務められた方の功績を称え、追悼する場ですが、このほかに広報としての役割があるからです。 どの事業規模の企業様であっても、社葬を通じて後継者を明確にし、今後の万全な体制や企業としての方向性を、取引先や株主、顧客、社員といったステークホルダーへ伝えられています。
- 火葬式と出棺式の違いは何ですか?
- 大きな違いは、お別れいただく時間です。火葬式は基本的に、火葬場で5分から10分のお別れのセレモニーを執り行うご葬儀です。一方、出棺式はご自宅や式場、ご安置施設に生花のシンプルな祭壇をご用意し、お別れのセレモニーも約1時間となります。ご会葬いただいた皆様は故人様のお顔をご覧になり、ゆっくり偲んでいただくことができます。
- 集会所で葬儀をするデメリットを教えてください。
- ご葬儀用に設計されていないので、受付、会計、待合所、食事のスペースが十分に取れない場合は、会葬された皆様で混み合うことがあります。また、天候や気温の影響を受けやすいこともデメリットです。 集会所でご葬儀を行われる際に、受付のスペースが取れない場合はテントを設置したり、気温が低い場合はストーブを用意するなど、状況に応じて対応いたしますので、ご相談ください。
- 集会所で葬儀をするメリットを教えてください。
- まず、使用料が一般的な式場より安価なことがメリットです。また、家から近いことも代表的なメリットです。
- 集会所を葬儀で利用する際は、申し込みはどのようにすればよろしいでしょうか?
- 地域の集会所は、窓口をしている責任者の方へ申し込みます。マンションなど集合住宅では、管理人さんに申し込みをします。 利用料金も含めて、事前に申込み窓口を確認しておくことをお勧めします。
- 集会所が葬儀で使用できないことはありますか?
- ありますので、事前に確認しておくことをお勧めします。
- 集会所でお葬式をする時に一番気をつけるポイントは何ですか?
- 集会所の下見です。集会所によって、親族控え室の有無、祭壇の飾り方、受付の場所などが異なり、それに応じて必要な備品が発生すると葬儀費用も変わってくるので、社員同行のもと事前に下見をすることをお勧めします。 お葬式の事前相談を見る
- 参列者が多いお葬式は、気苦労が絶えないと聞いたので、家族だけでお葬式を済ませた後、亡くなったことを知らせようと思いますが、お世話になった方々に失礼になりますか?
- そういったご葬儀のやり方もありますが、亡くなったことを知らせた後に、ご自宅へ多くの方が弔問に訪れて対応に苦慮することもあるので、十分検討していただくことをお勧めします。 専門知識を持った経験豊富なスタッフがおりますので、ご相談ください。
- 短時間で多くの方にお葬式の連絡をする方法を教えてください。
- 電話連絡は間違いが発生するので、FAXもしくはメールで連絡をします。 会社関係、友人、クラブ活動などの代表者の方に連絡をして、その方が各関係者へ訃報を連絡していく方法が一般的です。参列者が200人、300人でも、ご家族の方が連絡をするのは、親戚を含めて5~10人ほどです。 訃報連絡の文面はむすびすで準備をするので、ご安心ください。 FAXでの訃報連絡の見本を見る
- 大型葬をスムーズに行うポイントを教えてください。
- しっかりとした準備です。そのために、亡くなってから最低2日以上あけて葬儀を行うことを、お勧めしています。 多くの方を招く大型葬は、まず葬儀の日時・場所の連絡を漏れなく行うことから始まります。人数が多いと訃報が知れ渡ることに時間を要するので、日程をあけることは参列者の方々への配慮です。受付・会計などのお手伝い係の手配も必要となるので、余裕を持った葬儀日程をお勧めしております。 葬儀までの数日間、故人様のお体のケアは、むすびすにて万全に行うのでご安心ください。
- 予想以上に参列者が来た時は、どのように対応するのですか?
- 急な対応ができるように、むすびすが万全な準備をするのでご安心ください。 返礼品は予備を用意し、使用いただいた数だけ精算となるので、不足も無駄も発生しません。料理は、予備を用意してできるだけ不足がないようにします。
- 短時間で多くの方にお葬式の連絡をする方法を教えてください。
- 電話連絡は間違いが発生するので、FAXもしくはメールで連絡をします。特に来賓(VIP)へは、まず電話連絡をしてから、FAXもしくは訪問をします。お取引先には、FAXで連絡をします。 個人的なお付き合いの方々へは、友人、クラブ活動などの代表者の方に連絡をして、その方が各関係者へ訃報を連絡していく方法が一般的です。訃報連絡の文面はむすびすで準備をするので、ご安心ください。 FAXでの訃報連絡の見本を見る
- 社葬をスムーズに行うポイントを教えてください。
- 万全の準備を整えて臨んでいただくため、お亡くなりになられてから最低2日以上あけてご葬儀を行うことを、お勧めしています。 多くの方をお招きする社葬は、葬儀の日時・場所の連絡を漏れなく行うことが大切です。お取引先など、多くの方々に訃報が行き届くまでは時間がかかりますし、受付・会計などのお手伝い係の手配も必要となるので、余裕を持ったご葬儀の日程をお考えいただいた方がよろしいでしょう。 社葬では、来賓(VIP)のおもてなしも重要です。人員の配置やオペレーションを入念に確認しますので、ご安心ください。
- 予想人数を下回った場合、どんなデメリットがありますか?
- 参列者にご迷惑を掛けることはありませんが、余った料理は返品不可能なので、ご了承ください。 ただ、返礼品については、返品可能なのでご安心ください。
- 予想以上に参列者が来た時は、どのように対応するのですか?
- 急な対応ができるように、むすびすが万全な準備をするのでご安心ください。 返礼品は予備を用意し、使用いただいた数だけ精算となるので、不足も無駄も発生しません。料理は、予備を用意してできるだけ不足がないようにします。
- 参列者人数の予想ができないので、予想の手順を教えてください。
- まず、家系図を書いて親族の人数を予想します。親族の人数は、比較的容易に把握できます。 続いて、亡くなった方の関係者を予想します。年賀状や携帯電話の連絡先を参考にしながら、ご友人、ご近所の方、会社関係、サークル関係など、いくつかの区分に分けて5人、10人など概算で予想をします。その後、ご家族の関係者を、亡くなった方と同じように、いくつかの区分に分けて予想をしていきます。
- 会社の代表や役員が亡くなったら社葬を行うものですか?
- 社葬とは、企業が葬儀費用を負担して、ご葬儀を取り仕切る葬儀のことです。 会社の代表者の方であっても、ご家族様が窓口になり、ご家族様が葬儀費用を負担するのであれば、個人葬となります。社員のご葬儀であっても、会社が葬儀費用を負担する場合は、社葬となります。
- お通夜・告別式2日間のお別れが必要ですか?
- 最近はワンデイセレモニーと呼ばれる、告別式1日だけのご葬儀も増えてきました。1日だけのワンデイセレモニーは、費用を抑えることができ、参列者の負担も軽減されます。
- 菩提寺が遠方の場合、どうすればいいですか?
- 原則、遠方であっても葬儀には来ていただきます。 ただし、ご僧侶の都合もあるので、都合があわない場合は、菩提寺の許可を得てからご僧侶を紹介いたします。葬儀後の四十九日法要などは、菩提寺に依頼することになります。
- 戒名はいついただくのですか?
- 菩提寺の場合 : 遠方でない限り、葬儀をする前にお寺を訪問し、ご挨拶をかねて戒名の打合せをすることが多くなっております。詳しくは、菩提寺にお尋ねください。 むすびす紹介のご住職の場合 : ご家族様がご僧侶と直接お電話で話しいただき、故人様のお人柄などをもとに、戒名を授けていただきます。その後、お通夜(火葬)当日に戒名をお持ちいただきます。
- お布施はいつお支払いすればよろしいのでしょうか?
- 菩提寺の場合 : 菩提寺にお尋ねください。お通夜の日、もしくは葬儀を終えた後にお寺にお布施を持参することが多くなっております。 むすびす紹介のご住職の場合 : お通夜の始まる前にお渡しします。お布施は、現金でお支払いするのでご注意ください。お布施を入れる袋は私たちが用意いたします。
- 供花は受け付けますか?
- ほとんどの方が受け付けております。
- お香典は受け付けますか?
- 個人で執り行う場合は、お香典を受け付けることが多いです。 企業が執り行う場合は、税務処理もあるので、会社ごとに異なります。
- お別れ会、ホテル葬は、どんな儀式をするのでしょうか?
- 特に決まりはありません。献花、弔辞(お別れの言葉)、思い出映像、ビュッフェの食事など、完全オーダーメイドだからこそ、経験とノウハウが必要とされます。 むすびすでは、経験豊富なエンディングプランナーが対応いたします。
- お別れ会は密葬を済ませてから、何日後を目安として行いますか?
- 四十九日までに行うことが多くなっております。決まりはありませんので、準備やご都合を考え日程を調整することをお勧めします。
- どこのホテルやレストランでも、お別れ会をすることができるのですか?
- 対応できない場所もございます。地域、参列人数、交通アクセスなど、ご家族様のご希望にあった場所を提案いたしますので、詳しくはお問合せください。
- 学会員の家族が亡くなり友人葬で送ることにしました。喪主の私は学会員ではないのですが、誰に葬儀を取り仕切っていただけばよろしいのでしょうか?
- ご家族が所属していた地区の儀典部(責任者)の方へ相談します。 責任者の方が、段取りを整えてくださり、また受付・会計のお手伝い、ローカルルールなど、丁寧に教えてくれます。ご葬儀の詳細は、エンディングプランナーが責任者の方と打ち合せをさせていただきますので、ご安心ください。
- 友人葬の作法を教えてください。
- 一般的な仏教の葬儀と同じようにお焼香をします。学会員の方がお題目を唱えるため、座席が必ず祭壇を向いていることが特徴です。
- 友人葬とはどのような葬儀ですか?
- 友人葬は、故人様のご家族と創価学会の儀典部様(冠婚葬祭の儀式を行う儀典長様)が中心となり、ご会葬者の皆様でお題目を唱え、故人様のご冥福を願うご葬儀です。
- 一般葬のデメリットはありますか?
- 特にありませんが、参列者人数の予想が難しいことは事実です。 むすびすでは、参列者人数をできるだけ正確に予想をするようにお手伝いさせていただきます。また、急に予想を上回る参列者がいらっしゃった時に、万全の対応ができるように準備をさせていただきますので、ご安心ください。
- 供花や弔電(電報)をいただいた方へは、どのようにお礼をすればよろしいでしょうか?
- ハガキでお礼をいたします。ハガキはむすびすでご用意いたします。ご供花をいただいた方のリストもございますので、ご安心ください。 ご供花御礼ハガキの見本を見る ご弔電御礼ハガキの見本を見る
- 香典を受け取る受付や会計のお手伝いは誰に頼めばよろしいでしょうか?
- 原則、親族以外の方に依頼をします。お手伝いのお礼の目安は、1人あたり3,000円~5,000円です。 お手伝いを頼む方が見当たらない時は、ご親族の中から選出していただくことが一般的です。
- 参列者(お招きしたい方)に、葬儀の日時、場所をどのように連絡をすればよろしいでしょうか?
- 間違いがないようにFAXでの連絡をおすすめします。連絡用のFAX用紙は、むすびすにて作成いたします。 FAXでの訃報連絡の見本を見る
- 予想以上に参列者が来た時は、どのように対応するのですか?
- 急な対応ができるように、むすびすでは万全な準備をするのでご安心ください。 返礼品は予備をご用意し、使用いただいた数いただけ精算となるので、不足も無駄も発生しません。料理は、予備を用意してできるだけ不足がないようにします。
- 自宅で葬儀をするデメリットを教えてください。
- 参列者の人数によっては、受付、待合、食事をする場所の広さが足りず、混み合う可能性があります。エンディングプランナーがご自宅を拝見し、自宅葬を行うためのアドバイスをいたしますので、ご相談ください。
- 自宅で葬儀をするメリットを教えてください。
- 葬儀会場の使用料がかかりません。葬儀会場とは異なり、お通夜の後も時間の制限なく、故人様を偲んでいただけます。なにより、故人様にとって住み慣れた場所であり、ご家族様との思い出がつまったご自宅でのご葬儀は、故人様への想いにあふれたお時間になります。
- 自宅が葬儀で使用できないことはありますか?
- ほとんどありません。棺をご自宅へ入れることができればご葬儀はできます。ご葬儀の規模などによっては適さない場所もございますが、まずはエンディングプランナーまでご相談ください。
- 自宅でお葬式をする時に一番気をつけるポイントは何ですか?
- ご自宅の下見です。ご自宅によって、祭壇の飾り方、受付の場所、食事の場所などが異なり、それに応じて必要な備品が発生すると葬儀費用も変わってくるので、社員による下見、並びに事前相談をお勧めします。 お葬式の事前相談を見る
- 無宗教葬をした後の四十九日法要や仏壇などはどうすればいいのですか?
- 無宗教なので特に決まりはありませんが、四十九日、一周忌など定期的に供養の場を設けることをお勧めしております。仏教のように集まってお経をあげるような儀式はありませんが、皆様でお食事を召し上がりながら、旅立たれた方を偲ばれてはいかがでしょうか。 仏教でいう仏壇、位牌についても、無宗教では決まったものはありません。旅立たれた方を偲ぶお品として、ご遺灰の一部をお納めするデザイン性の高いミニ骨壺やペンダントなどがございますので、よろしければご紹介いたします。
- 無宗教葬では、納骨(お墓)はどのようにするのですか?
- 霊園や納骨堂、永代供養墓など、納骨は従来と同じ形式となります。 最近では、散骨や樹木の下に収める樹木葬にする方もいらっしゃいます。
- 菩提寺がありますが、無宗教葬をすることはできますか?
- ご住職と相談する必要があります。代替え案として、仏教儀式の前後のお時間(お通夜のお経の後など)に無宗教葬を取り入れる方法もあります。
- 音楽葬はできますか?
- はい、承っております。音楽葬は、無宗教葬の中でも最近増えているご葬儀のスタイルです。故人様が生前お好きだった音楽を中心としたご葬儀を「音楽葬」と呼びます。 録音された音源をCDでお流しするほか、ピアノや弦楽四重奏などの生演奏による「献曲」、合唱による「献歌」、または音楽を聴きながら軽食でおもてなしをする「ティーセレモニー」など、自由な形式で執り行うことができます。無料の事前相談で、音楽葬に適した式場や式次第をご提案させていただきます。
- 無宗教での葬儀を、親戚や知人から反対されることはありますか?
- ひと昔前であれば、伝統を重んじる方などに反対されるケースもあったようですが、最近はほとんどありません。親しい方だけを呼ぶ家族葬の増加など、お葬式への考え方が大きく変わっているのも要因です。 むすびすでは、お葬式を始める前に無宗教でお葬式を進めていくことを、司会よりご説明させていただき、ご会葬の皆様へご理解いただいております。また、案内ボードでご説明することもあります。
- 無宗教葬では、どんな儀式をするのでしょうか?
- 代表的な儀式は献花と呼ばれる、お花を供える儀式です。仏教では、お経やお焼香がありますが、無宗教では決まりがありませんので、ご家族と打合せをしながら儀式の内容を決定します。
- 神社でご葬儀を行うことはできますか?
- 神道において死とは穢れ(けがれ)とされているため、神様の聖域である神社でご葬儀を行うことはできません。ご自宅または式場にて執り行うのが一般的です。
- 神道のお葬式の式次第を教えてください。
- 神道葬も、仏教と変わりません。 ただ宗教の違いがあるので、呼び方の違いがあったり、雰囲気が違ったりしますが、ご家族が困るような大きな違いはありません。お参りの仕方が、お焼香が玉串となり、亡くなった方が仏様ではなく神様になります。専門知識を持った経験豊富なスタッフが対応しますので、ご安心ください。
- 神主さんを紹介していただけますか?
- もちろん紹介いたします。 神主(神官)さんへのお礼も、むすびすでは明確に定めております。仏教ではお布施ですが、神道では祭祀料(さいしりょう)と呼びます。
- 神道に戒名はありますか?
- 御霊となった故人様のお名前として、生前のお名前に加え、諡号(おくりな)をつけます。 成人男性は「大人命(うしのみこと)」、成人女性は「刀自命(とじのみこと)」などが一般的な諡号ですが、神主様が故人様のご年齢、生前のお考え、ご家族の希望などをもとに決めていきます。 戒名とは違い、諡号にランクはございません。
- 神道葬の作法を教えてください。
- 仏教葬では必ず霊前へのご焼香が行われますが、神道葬ではお焼香は行いません。 神道葬では玉串奉奠(たまぐしほうてん)という、玉串と呼ばれる葉のついた枝を神前にお供えします。 慣れない作法ですが、むすびすでは作法の説明書を参列する皆さまにお渡ししておりますので、ご安心ください。 神道葬の作法説明書を見る
- 神道のご葬儀の考え方は?
- 古来より日本人は神の世界から生まれ、やがて一生を終えると神々の世界へ帰っていくと考えられてきました。よって神道のご葬儀は、故人様に家の守護神となっていただくための儀式として執り行われます。 遷霊祭で、故人様の御霊(みたま)を霊璽(れいじ/仏教での位牌にあたるもの)に移し、ご家族の手によってお祀りすることで、故人様が子々孫々その家をお守りするとされます。
- 直葬(火葬式、火葬のみ)との違いは何ですか?
- 何の儀式もせず、火葬前に短い時間でお別れをするのが直葬です。 1日葬は、一般的な葬儀の形からお通夜を省いたお葬式なので、限りなく一般的なお葬式と同じとお考えください。
- 1日葬でも、斎場に泊まって故人といっしょに過ごすことはできますか?
- 前日からご葬儀の準備で斎場を使用するため、宿泊可能な斎場であれば故人様と一晩お過ごしいただけます。宿泊できない斎場であっても、準備をしている間はご親族や近しいご友人だけで、お別れのお時間をゆっくりお過ごしいただけます。
- 2日間の葬儀に比べて、どんな費用が抑えられるのですか?
- お通夜がないので、お清め(お食事)の費用がかかりません。私たちにご僧侶や神主様の手配をご依頼された場合は、お布施や祭祀料に含まれるお車代、お膳料1日分を抑えることもできます。また、遠方からのご会葬者がいらっしゃる場合は、宿泊代も抑えられます。 式場によっては、利用料金が半額になることもありますが、ほとんどの場合は、お通夜がなくても前日から設営で使用するので、通常料金となります。
- 1日葬はどんな宗教でも行うことができますか?
- むすびすでは対応可能です。 ただし、お付き合いのある宗教者様(菩提寺様など)がいらっしゃる場合は、相談してから執り行います。
- 菩提寺があっても火葬式はできますか?
- 菩提寺の許可をいただく必要がありますので、火葬式をする前にご僧侶と相談をします。
- 戒名をいただきたいのですが、火葬式でも戒名をいただくことができますか?
- もちろん可能です。火葬式は、ご僧侶に読経いただくこともできますし、読経はしないで、戒名だけいただくこともできます。
- 火葬式に参列者人数の制限はありますか?
- 制限はありませんが、シンプルなご葬儀なので、少人数で執り行うことが一般的です。
- 火葬式はどこで式を行うのですか?
- 火葬場、もしくはご自宅から出棺し、火葬場でお別れのセレモニーを執り行うのが一般的です。葬儀場を借りる場合もありますが、葬儀場使用料が発生します。
- 火葬式とはどんなお葬式ですか?
- お通夜や告別式を行わない、シンプルなご葬儀のことです。 代表的な式次第 ご家族集合 お別れの儀(お棺へお花、愛用品を納めます) 火葬 収骨(遺骨を骨壷へ納める儀式)
- 家族葬のご案内をしなかった方に、お葬式を終えたことをどうやってお知らせすればよろしいでしょうか?
- はがきでお知らせすることが一般的です。はがきの手配も私たちでお手伝いさせていただきます。 ご逝去お知らせハガキの見本を見る
- 家族葬で香典や供花を、いただいてもよろしいのでしょうか?
- 多くのご家族様はいただいていらっしゃいます。ご辞退を希望される際は、事前にお電話もしくはFAXでお伝えするようにいたします。 お断りしたにもかかわらず、ご会葬者が「どうしても」と置いていかれたお香典に対してはお返しをし、故人様に代わって感謝の意を示しましょう。また、ご弔電やご供花が届いた場合も、お礼を申し上げましょう。 香典・供花辞退のご案内の見本を見る
- 亡くなったことを近所の方に知らせずに、家族葬を執り行うことはできますか?
- 可能です。病院などご自宅以外で亡くなられた場合、ご自宅ではなくご安置施設をご安置場所に選ばれれば、ご近所の方に知られることはありません。 ご自宅でのご安置を希望される場合、明るい時間帯は控え、ご家族様のご都合に合わせて深夜・早朝にご安置いたします。また、ご葬儀のお打ち合わせでスタッフがご自宅に伺う際、ご要望いただければ、葬儀社の社員と分らない礼服以外の服装で伺います。
- 家族だけのお葬式は、ご近所や会社関係の方などに対して、失礼にあたりますか?
- 失礼ではありません。最近では、家族葬を選ばれる方が増え、私たちがお手伝いさせていただくご葬儀の8割を占めています。どなたにもお伝えせず行われる方法もありますが、参列を辞退いただくことをお伝えして行われる方法もあります。ご家族様のご要望に合った方法をご案内いたしますので、ご安心ください。 会葬辞退のご案内の見本を見る
- 家族葬のデメリットはなんですか?
- ご親族や近しいご友人だけでご葬儀を執り行うため、連絡しなかった方々から、「亡くなったことを教えてほしかった」と言われる場合があります。 また、「お世話になった人だから、お焼香をあげさせてほしい」とご葬儀後にご自宅を訪れる方もいるため、その度に弔問への対応が必要になります。
- 家族葬のメリットはなんですか?
- 家族葬には大きく2つのメリットがあります。1つ目は、費用を抑えられることです。参列者はご親族や近しいご友人など少人数で規模も大きくないため、司会や多数の運営スタッフ、大型の式場が不要なケースが多く見られます。人数が少なければ少ないほど、お通夜や告別式での飲食代、返礼費用も抑えることができます。2つ目は故人様とゆっくりお別れいただけることです。参列者はご親族や近しいご友人だけなので、弔問や挨拶などに時間を取られることなく、故人様への愛情や感謝をお伝えいただけます。
- 家族葬と密葬は違うのですか?
- ご親族だけで執り行われるご葬儀を、従来は「密葬」と呼び、多くの場合は密葬の後に火葬し、後日改めてお別れ会などを行うものでした。 一方、1990年代に登場した「家族葬」は、ご親族や親しいご友人など、喪主様が参列者を限定し、通夜・告別式を執り行った後に火葬するものです。
- 家族葬とは何ですか?
- 家族葬は、勤務先の関係者や近隣の方々などの参列をお断りし、ご親族やご友人など、ごく近しい方々で故人様をお見送りいたします。 家族葬と呼ばれていますが、あくまでも「ご家族様を中心にしたご葬儀」という意味で、ご家族様は参列者をお選びいただき、人数を限定することができます。

読み取ると、
すぐにダイヤル
できます
弔事のお役立ちコンテンツ
万が一の時のために、知っておきたいお葬式のこと。