家族葬とは?
家族葬とは、ご家族様がご葬儀にお呼びする方をあらかじめ限定し、比較的少人数でゆっくりお別れができる意味深いご葬儀です。ご葬儀の名前に「家族」と付くので、ご家族様だけで行うものだと思われがちですが、ご親族や故人様と親しかった友人の方もお呼びできます。

1これを知れば大丈夫!家族葬がわかる6つのポイント

家族葬を行うにはどのようにしたらよいのでしょうか。 第1章では家族葬を行う上で知っておきたい6つのポイントを紹介します。
-

1.9割以上のご家族様から選ばれている家族葬
家族葬を行うご家族様は年々増えています。お葬式のむすびすが2021年1月に首都圏1都3県でお手伝いしたご葬儀から、規模やスタイルで分類し、その中から家族葬にあてはまるご葬儀の割合は約92%となり、家族葬は首都圏の主流であることが分かります。家族葬が増えたことで、ご葬儀への参列をお断りする、会葬辞退の案内もスタンダードになり、失礼と思われることもありません。
-

2.家族葬は参列者の人数をあらかじめ決められる
家族葬の明確な定義は存在しないため、呼びする方の範囲や人数に決まりはありません。ご家族の意向によって親族にも知らせずに家族だけで送る密葬に近いスタイルもあれば、大手エンターテイメント事務所の創業者のように、生前にファミリーのように親しく付き合っていた仲間たちが100名以上集って執り行うのも家族葬です。家族葬とは単なる小規模なご葬儀ではなく、ご家族様があらかじめ参列者の人数を決めることができるご葬儀のかたちです。家族葬の主な注意点としては、参列者をどこまで招待するかの線引きが曖昧であることが挙げられます。これにより、招待されなかった知人や友人が不快に感じる場合もあるため、通知の仕方や説明には配慮が必要です。
-
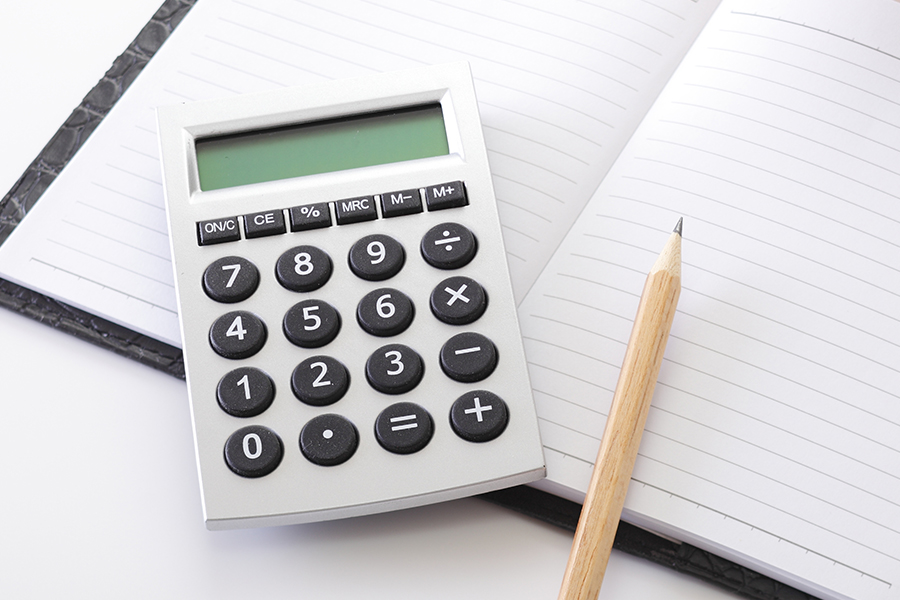
3.家族葬の平均費用は約105.9万円
家族葬の費用は、参列者の人数と葬儀スタイルによって異なります。一口に家族葬と言っても、故人様と同居していたご家族様だけで送るご葬儀もあれば、故人様と親しく付き合っていた方々に限定して、最期のお別れの時間をゆっくり過すなど、そのスタイルはさまざまです。
-

4.家族葬が行える斎場・葬儀場はたくさんある
家族葬は葬儀をあげられる場所であれば、どこでも行うことができます。一般のご葬儀と同じように、故人様やご家族様のご希望によって、自由に斎場を選ぶことができます。最近は家族葬に最適な10~30名まで着席できる広さの斎場も増えています。
-

5.家族葬はこんなご家族様に選ばれています
-
・弔問客への対応などを気にせず、故人様との最期の時間をゆっくり静かに過したい。
-
・ごく近しい親戚や気心の知れた友人だけで、故人様との思う出を語り合いたい。
-
・故人様と親しかった少数の参列者に、しっかりおもてなしをしたい。
-
・親族や友人が高齢なので、長時間の葬儀式に参列するのが大変。
-
・安く済ませたい訳ではないが、大げさなご葬儀や無駄な費用はかけたくない
-
-

6.感染防止を第一に考えた家族葬について
2021年6月現在、緊急事態宣言は解除されましたが、新型コロナウイルス感染防止を第一に考え、参列者数の制限、葬儀日数の制限、お食事提供の制限、インターネット利用をするなど、ご家族様の安全に配慮した家族葬が注目されています。
- 通夜を行わずに、1日で行う少人数の家族葬が選ばれています。
- 家族葬のご相談や打ち合わせを、スマホやパソコンなどを使ってすることができます。
- ご会葬者へのお通夜・告別式料理のご提供を控え、代わりにご自宅でお召し上がりになれるカタログギフトをお渡しいたします。
- 葬儀スタッフがご家族様の安全を第一に考え、様々な感染防止対策に取り組んでいます。
2家族葬の準備と流れ
-
1.危篤時・ご逝去の準備
参列者をご親族や近しいご友人に限定するのが家族葬です。あらかじめ、お呼びする方、お呼びしない方を決めておけば、「万が一」の時に誰へ連絡するか迷うことはありません。

-
2.ご臨終
あらかじめ決めておいた葬儀社へ、お迎えの場所や時間の連絡します。ご近所の方に、不幸があったことを知られたくないというご家族様には、ご自宅以外へのご安置をお勧めいたします。

-
3.故人様の搬送と準備
寝台車と分からない車や、葬儀社のスタッフだと分からない服装での搬送を依頼できます。また、ご近所の方がお休みになっている、深夜・早朝の搬送であれば、知られることもありません。

-
4.ご葬儀の準備
ご葬儀の日程や場所をご案内する訃報には、故人様の意志で家族葬を行うこと、家族葬への参列をお断りすることを明記しましょう。香典や供花を辞退する場合は、併せて明記しましょう。

-
5.お通夜
お通夜は、故人様とお過ごしいただく、最期の一夜です。参列者が親しい方だけなので、故人様と最期の時間をゆっくり過ごすことができます。お通夜後に故人様と最後の一晩を一緒に過ごしたいというご家族様は、斎場や会場が宿泊可能か確認しましょう。布団やシャワー、浴室を備えた斎場や会場もあります。

-
6.葬儀・告別式
故人様への感謝とともにお見送りをする、お別れの儀式です。閉式後に火葬場へのご出棺となります。

-
7.ご葬儀後
家族葬にお呼びしなかった方、お知らせをしなかった方へ、家族葬を終えた報告のはがきを送りましょう。はがきを送るタイミングは、四十九日の法要を終えた後や納骨の後、年末の喪中はがきでお知らせするなど、ご家族様のご都合や送る方の関係によってさまざまです。

3.家族葬で葬儀社を選ぶポイント
ご葬儀は、故人様との大切なお別れの儀式です。やり直しができないだけに、葬儀社を「安いから」「大手だから」「地元だから」といった理由だけで選ぶと、後悔につながることがあります。まずはインターネットで比較して、4社ほどをピックアップしてお見積りを取りましょう。「ご葬儀をご希望になる地域」「式のイメージ」「予算は○円以内」など、おおよその希望や、不安に思われている点を事前に伝えておくと、比較しやすくなります。最初の見積りをとにかく安くするために、内容や費用のあいまいな資料を送る葬儀社が問題になっています。
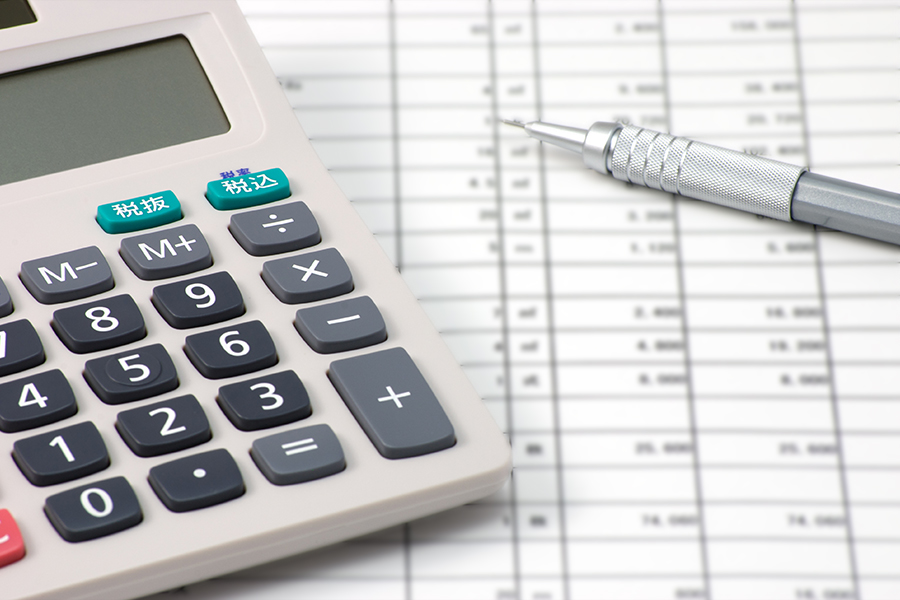
お見積もりのチェックポイント
- 分かりやすいパンフレット、会社紹介がある。
- 写真付きで商品を紹介している。
- ひとつのサービスだけでなく、選択肢を示している。
- 明細がはっきりした見積書がついている
(会葬者の予測人数・祭壇・お棺の種類・料理・返礼品・お布施の額・数量などが明確)。 - 食事費用・返礼品まで含めた総額を提示している。
- セット内容と、追加項目の違いがはっきり説明されている。
いつ連絡をしても専門相談員が対応し、どんな質問にも的確に応えられる葬儀社を選ぶことが重要です。
4.ほかのご家族はどうしている?さまざまな家族葬のスタイル
親しい方だけで見送る家族葬は、ご家族様の想いを優先し、形式にとらわれないご葬儀ができます。「特定の信仰がない」「お別れでしんみりしたくない」というご家族様の中には、読経や焼香といった宗教儀式のない無宗教葬やお別れ会を選ぶ方もいます。
また、高齢の方の体調やご親族の日程の都合などから、お通夜を行わず、告別式の1日だけでお別れする1日葬も増えています。


「家族葬で、故人様らしいご葬儀、ご家族様が望まれるご葬儀にするためには、故人様が大切にしてきたことや生き方を、ご家族様が大事にすることです。
また、故人が最期にしたかったことで送ってあげることで、より納得のできるお別れになります。
家族葬のスタイルに迷ったときは、複数の葬儀社に相談して、故人様およびご家族様のご要望を形にしましょう。
- 趣味や思い出など、想いが深いことを聞いておく(想い出の品の保管場所を確認)
- 最期に行きたい場所を聞いておく。
- 最期に行きたい場所を聞いておく。
5.家族葬はこんなこともできる。
想いを形にした3つの葬儀事例を紹介
-
母と約束したお花見
「宴会のようなお葬式を望んだお母様のために
母と約束したお花見 お祭りや宴会、お花見といったにぎやかなことが大好きだった、浅草生まれのお母様。 毎年の小松川千本桜のお花見では、ご家族やご友人と河川敷でバーベキューをするのが恒例でした。
ご葬儀の打ち合わせの時に、お花見の話を聞いた担当プランナーは、桜の枝をご用意しました。 そこに、ご家族様みんなで選んだお母様の写真をパネルとして飾ったことで、会葬者の方々は「あの時は、こうだったよね」と、お母様と過した思い出話が尽きることがありませんでした。


ご葬儀の後、ご家族様はお母様のレシピを思い出しながらワンタンを作り、お骨壺の横にお供えしました。
喪主様は、「元気になったら一緒にお酒を飲もうと約束していた息子と、最後にお花見でお酒を飲むことができて、母も嬉しかったと思います。母との別れは悲しいけれど、最期に“今までありがとう”と想いを伝えることができました」と、担当プランナーに語られました。
-
愛犬とのお別れ
ペットと一緒のお別れは、家族葬だからできるスタイル
愛犬とのお別れ 亡くなられたお父様は、愛犬・タロをわが子のようにかわいがり、長い入院中も「タロは元気か?」とずっと会いたがっておられたそうです。
「親父に、タロと会わせてやりたかったな」という喪主様の言葉を聞いた担当プランナーは、「火葬場まで、タロちゃんを連れて来られてはいかがでしょう」と提案しました。
お父様をお見送りする日の朝。火葬場の外に設けた、つかの間のお別れの時間。お棺のふちから、じっとお父様のお顔を見つめているタロは、まるでお別れを言っているように見えました。喪主様は、「親父が会いたがっていたタロと、最期に直接お別れすることが叶い、家族葬を選んでよかった」と話されました。

-
父を囲んだ家族だけの食事会
家族、水入らずの時間を
徹底的に追求する「家族だけで葬儀をしてほしい」。それがお父様の遺言でした。特定の宗教には縁がなく、形式にとらわれないお父様のご葬儀は、ご家族様と相談して、無宗教での家族葬にすることになりました。ご家族様のご要望は、「堅苦しい儀式はせず、最後に家族だけでゆっくり過ごしたい」ということでした。
そこで、担当プランナーは「お父様を囲んだ食事会」をご提案いたしました。お通夜当日の斎場には、祭壇の代わりにお父様の写真や、お父様が趣味で描いていた絵画がきれいに飾られていました。お父様の眠る棺を囲むように、ソファとテーブル。BGMは、お父様がよく聞いていた音楽です。


ご家族様は自宅のようにくつろいだお食事会を行ない、お父様の思い出話をしながら、明け方まで語り明かされました。翌朝から仕事があったご家族様のために、告別式も朝早く設定。特別なことはせず、全員が集まり、お父様を囲んでお茶を飲みながらゆっくり過ごしました
喪主様は、「思い返せば、家族が父とこんなにゆっくり過ごせたのは、最初で最後だったかもしれません。家族が父の近くに集まり、手を合わせるだけで十分。むしろそれが父らしい」と、担当プランナーに話されました。
6.家族葬の注意点を知ることでトラブルを回避
多くのご家族様から選ばれている家族葬ですが、メリットがある一方で、
お呼びする方を限定することによる注意点や落とし穴もあります。
家族葬の注意点を知ることで、トラブルを避けることができます。
-

1.お呼びする人数によって、家族葬のプランや費用は変わります
家族葬はご家族様や故人様が、あらかじめ参列者の人数を決めておくことができるご葬儀です。
ご家族様や親族、故人様と親しくしていた方など、少人数で行うご葬儀と思われがちですが、ご葬儀の規模や参列者の人数に制限はありません。ご葬儀にどこまでお呼びするか決まりがないので、お考えがまとまるまで時間がかかります。大切な方が旅立たれた直後は、なおさら考えがまとまらないものです。万が一の時、ご親族や故人様のご友人をどこまでお呼びするか、事前に考えておきましょう。 -
2.連絡するか迷った方は、お呼びしたほうがいい
連絡すべきかどうか迷う方がいる場合は、お呼びすることをお勧めします。お呼びしない方がご親族の場合、後から「どうして自分だけ呼ばれなかったのか?」と言われる可能性があります。また、ご葬儀後に訃報を知った方が、「焼香を上げさせてほしい」とご自宅へ弔問に訪れることも考えられます。
-

3.お呼びしない方には、会葬辞退のご案内や訃報通知を送るのがマナー
家族葬は参列者の人数を決められるご葬儀なので、お呼びする方だけにご案内するのが一般的です。しかし、ご葬儀前にご逝去を知らせなくてはいけない場合は、会葬辞退の案内で「故人並びに遺族の意志により、近親者にて家族葬を執り行う」ことを伝えましょう。家族葬が増えたことで、会葬辞退の案内もスタンダードになり、失礼と思われることもありません。お呼びしなかった方には、ご葬儀後に「葬儀は近親者のみにて執り行った」ことを訃報通知で報告するのがマナーです。
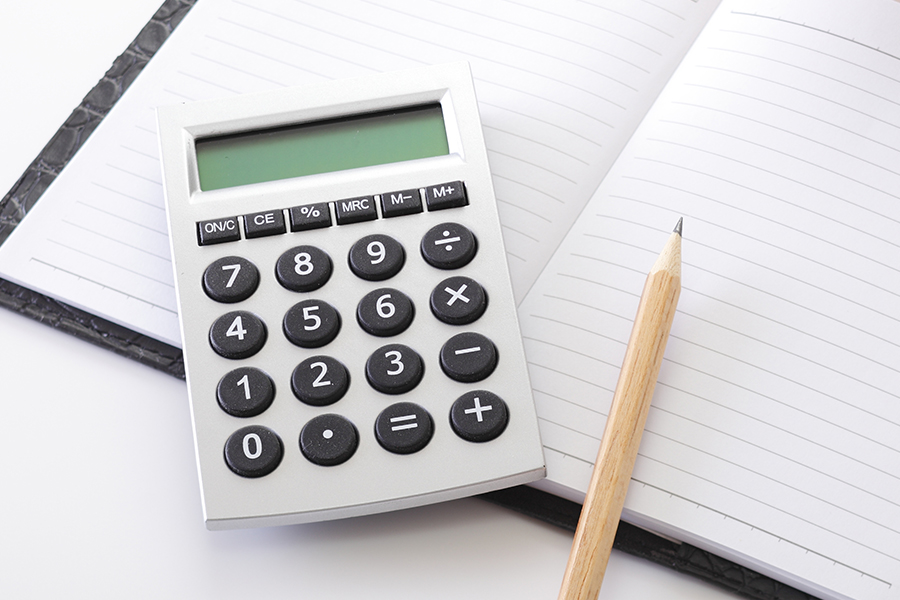
4.香典の総額が少ないので、一般のご葬儀より支払いが多くなる可能性も
参列者を限定する家族葬は、ご近所やお仕事関係の方が参列する一般葬に比べ、受け取る香典の総額が少なくなるので、一般葬よりも費用の負担が多くなる可能性もあります。また、ご葬儀にお呼びしていない方から、後日「以前に香典を頂戴したので」と香典を渡される場合があります。故人様へのお気持ちなのでお断りせず、後日、香典返しをお渡ししましょう。
5.ご近所に知られてしまう意外な落とし穴
病院で亡くなった故人様をご自宅へ運ぶ寝台車や、打ち合わせのためにご自宅を訪問する葬儀社のスタッフが、ご近所の方の目にとまる場合があります。 ご近所の方々に知らせたくない場合は、あらかじめ葬儀社に対応を相談しましょう。
家族葬とは?のまとめ
多くのご家族様から選ばれている家族葬は、故人様と親しかった参列者だけで、最期のお別れの時間をゆっくり過ごせるご葬儀です。
親しい方だけで見送る家族葬は、故人様とご家族様の想いを優先し、形式にとらわれないご葬儀ができることから、家族葬を行うご家族様は年々増えています。
家族葬は単なる小規模なご葬儀ではなく、ご家族様があらかじめ参列者の人数を決めることができるご葬儀のかたちで、お呼びする方の範囲や人数に決まりはありません。
連絡すべきかどうか迷う方がいる場合、お呼びするほうが後々のトラブルを避けることにつながります。
家族葬の行える斎場は、一般のご葬儀と同じように、故人様やご家族様のご希望によって自由に選ぶことができます。
家族葬を依頼する葬儀社は、「安いから」「大手だから」「地元だから」といった理由だけで選ぶと、後悔につながることがあります。複数の葬儀社からお見積りを取ることをお勧めします。
家族葬のよくある質問
-
家族葬とは何ですか?
-
家族葬とは、ご家族様がご葬儀にお呼びする方をあらかじめ限定し、ゆっくりお別れができるご葬儀です。 ご葬儀の名前に「家族」と付くので、ご家族様だけで行うものだと思われがちですが、ご親族や故人様と親しかった方もお呼びできます。
-
家族葬をするにはどうすればいいですか?
-
家族葬を行うことに意見が分かれることもありますので、まずは家族葬を行うべきかどうかを、ご家族で事前によく話し合いましょう。
-
家族葬はどこでできますか?
-
家族葬は、参列者数に適応した葬儀場・斎場、またはご自宅にて執り行うことができます。 斎場には「公営」と「民営」があり、故人様や喪主様のお住まいの地域に公営斎場がある場合は、費用などで優遇されてご利用いただくことができる場合がございます。
-
家族葬のメリットとデメリットは何ですか?
-
メリットは、参列者が親しい方であるため、故人様とプライベートな空間でゆっくりお別れいただけることです。 また、小規模なので、お通夜や告別式での飲食代、返礼費用も抑えることができます。 デメリットとしては、連絡しなかった方に「亡くなったことを教えてほしかった」と言われたり、ご葬儀後ご自宅に多くの弔問客が訪れ、その対応にお疲れになることもあります。
-
コロナ禍でも家族葬はできますか?
-
はい、できます。 感染予防を第一に考え、参列者数の制限、葬儀日数の制限、お食事提供の制限、インターネット利用をするなど、ご家族様の安全に配慮した家族葬が注目されています。
私たちが大切な旅立ちを
お手伝いします。
ご葬儀への不安や疑問を解消するため、専門の相談員が24時間365日対応いたします。
残されたご家族が豊かに生きるために、私たちが精一杯お手伝いいたします。
-

中西 実
-

谷花 美穂
-

有坂 立朗
-

高野 孝徳
-

平川 雅彦
-

山本 衣理
-

小野崎 敦
-

植竹 祐公
-

鳥本 拓
-

古家 崇規
-

吉岡 雄次
-

能藤 有紗
-

中村 元紀
-

廣間 一生
資料請求・ご相談はこちらから
既に他の葬儀社で御遺体を搬送されたあとでもご依頼可能です。
大切な方との最期のお別れは、信頼できる葬儀社をお選びください。
-
24時間365日。専門のスタッフが対応します。
0120-74-9072
どんなことでもお気軽にご相談ください。

-
-
24時間365日対応 / 相談無料 / 通話無料
0120-74-9072
-
ご危篤・ご逝去お急ぎの方
-
事前相談
-

後悔しない為のお葬式Book同封 無料資料請求はこちら




























